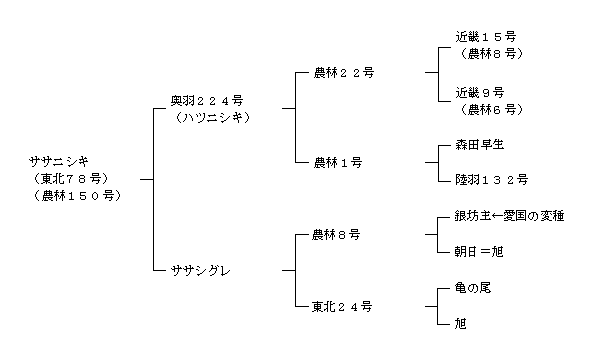|
|
| 用途に合わせた銘柄選び |
| おコメのルーツは、? |
| 「越後屋、おぬしも相当の・・・」の、<米問屋>って何? |
| お米の家系図 |
| 無洗米について教えて |
| 多様化米について |
| お米の栽培方法について教えて。 |
| お米の単位 |
| 田んぼの単位 |
用途に合わせた銘柄選び
| おにぎり | コシヒカリ・ひとめぼれ |
| 寿司 | ササニシキ・ハナエチゼン・ハツシモ・あきたこまち 日本晴+コシヒカリ |
| チャーハン・ピラフ | キララ397・日本晴・ほしのゆめ |
| 丼 | はえぬき・ハナエチゼン・ササニシキ・キヌヒカリ |
| 炊きこみご飯 | 夢ごこち・ミルキークイーン+コシヒカリ・コシヒカリ・ ひとめぼれ |
| お弁当 (冷めても美味しい) |
あきたこまち・夢ごこち・ミルキークイーン+コシヒカリ |
| 毎日何となく食べている「おコメ」は、どこで生まれ、どうやって日本に伝わってきたのでしょうか。 本当のことを言って、おコメの発祥、伝わりかたなどは、まだよく分かっていないのです。 中国湖南省では、今から12000年前には熱帯ジャポニカ種(赤米)が栽培されていた事がわかっています。日本には縄文初期の6000年まえに伝わっています。これは中国浙江省に7000年前に伝わり、漁労民より中国に伝わったと考えられています。ただ、この頃は、焼畑による陸稲でした。当時は今より温暖な気候であったため、伝わりやすかったようです。また、この頃にはひえやあわもいっしょに栽培されていました。今の水稲は5500年前に中国江蘇省に始まり、熱帯ジャポニカ種が進化して栽培されていました。ここから朝鮮半島に行き、当時交易が確認されている縄文人により日本に入ってきました。入ってきたのは今から2600年前縄文後期。このころ、温帯ジャポニカ種も入ってきて、日本中に広がったと考えられています。伝えられた場所は、今の北九州あたりと言われています。当時は、熱帯ジャポニカ種と温帯ジャポニカ種を交配させることで、雑種が作られ、これが早稲種であったことから、一気に青森のあたりまで広がっています。時代は弥生時代。 北緯41度でも遺跡が確認されています。現在では、北緯44.43度北海道の遠別町が最北端と言われています。 |
| テレビの時代劇に、ときおり「米問屋」の善玉、悪玉が登場しますが、米屋というのは見かけたことがありませんね。また、その当時の「米問屋」や「米屋」が、どのような事を仕事として行なっていたのか、あまり知られていません。 では米屋は、いったい、いつ頃から生産者と消費者の間に立って、おコメを商品として取り扱うようになったのでしょう。 一番古くは、奈良時代の平城京にある「東西市」に、米店がもうけられいたことが事実として残っております。 また、平安時代、平安京の市にも「米店」が設置され、その後、「問丸」という業者が、中世の米問屋と輸送業を行なうようになりました。このことからも、「米屋」の方が「米問屋」よりも先に登場したことになります。江戸時代になると、米販売に対して、いろいろな役割に分化されるようになってきました。
|
||||||||||||||